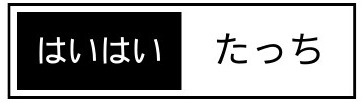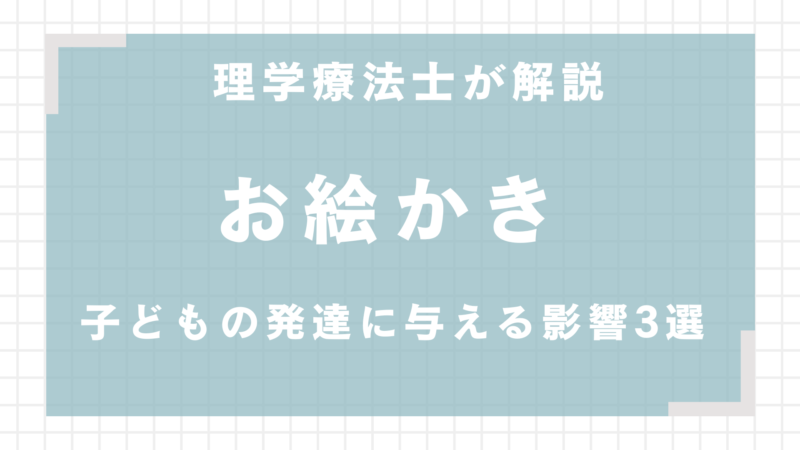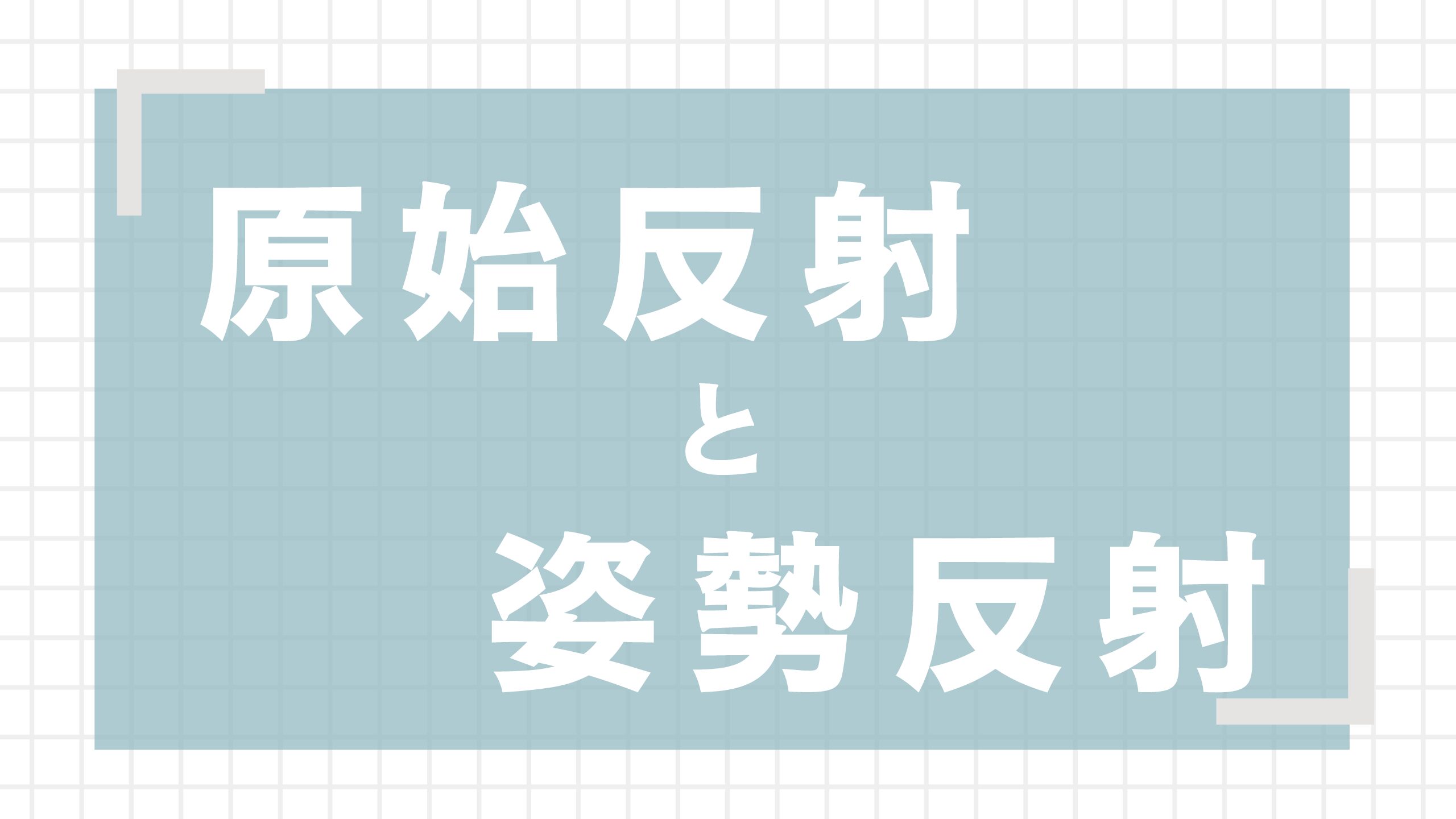子どもは「遊び」の中でいろんなことを体験しながら学び、発達に対して非常に重要な役割を果たします。特に「お絵かき」は子ども達も大好きで、自宅でも手軽に行うことができ、運動・認知・情緒面に幅広く良い影響を与える活動です。
本記事では、理学療法士の視点から「お絵かきが発達に与える良い影響」を3つに分けて解説し、J-STAGEなどで公開されている文献を参考に、エビデンスも紹介します。
手先の巧緻性(器用さ)を高める
お絵かきでは、鉛筆やクレヨンを持って「つまむ・握る・動かす」といった手指の細かい操作が必要になります。つまむ・握るという操作には数段階の工程がありますが、まずはどんな形でも鉛筆やクレヨン握って書くことが大切です。
筆記用具の操作や書くという工程により手先の器用さ(いわゆる「巧緻性」)の発達の向上が期待されます。
理学療法の現場でも、手指の発達支援としてお絵かきはよく使われます。発達性協調運動障害(DCD)や脳性まひのあるお子さんに対して、線や図形を描く練習は運動制御の向上に役立つことが報告されています。
▶ エビデンス
中村悠介ほか(2022)『鉛筆操作課題と手指の運動発達の関係』日本作業療法学会誌,41(1),22-29.
▷J-STAGEにて全文閲覧可能。
認知機能・空間認識の向上
お絵かきは、自分が思い描いたものを書くこともあれば、おもちゃや絵を見ながら模写することもあると思います。
自分が描きたいものを書く場合、<イメージする>ことが必要になり、記憶力や集中力が必要となります。また模写する場合も、見た対象物を覚える→対象物から視線を白紙に移す→描くという過程が行われます。この一連のプロセスにより視空間認知・記憶力・集中力など、さまざまな認知機能が向上することが期待できます。
また、左右・上下といった空間概念の理解にもつながり、視知覚に課題のあるお子さんにも有効です。
▶ エビデンス
森悠紀ほか(2018)『描画課題における視空間認知と運動制御の関連』臨床作業療法,35(6),621-626.
▷J-STAGEにて閲覧可能。
自己表現・情緒の安定に役立つ
お絵かきは、言葉でうまく伝えられない気持ちを表現する手段にもなります。「楽しい」「悲しい」「不安」など、感情を色や形でアウトプットすることで、情緒の安定やストレスの軽減につながる可能性があります。
療育やプレイセラピーの現場でも、お絵かきは感情の整理や自己肯定感の向上に用いられています。
▶ エビデンス
大竹真奈(2019)『描画による自己表現と感情調整の関連』日本心理学会第83回大会発表論文集
▷J-STAGEにて閲覧可能。
お絵かきを発達支援に活かすコツ
- 環境を整える:安定した姿勢がとれる机と椅子を用意する
- 道具を工夫する:太めのクレヨンから鉛筆へ、段階的にレベルアップ
- 記録を残す:描いた絵の変化を写真などで残して成長の確認にも
まとめ
お絵かきは、単なる遊びではなく、
- 手指の巧緻性の向上
- 認知機能・空間認識の発達
- 自己表現・情緒の安定
など、多方面で子どもの発達をサポートする重要な活動です。
家庭でも療育現場でも取り入れやすく、発達支援の第一歩として非常におすすめです。
参考文献
- 中村悠介ほか(2022)『鉛筆操作課題と手指の運動発達の関係』日本作業療法学会誌,41(1),22-29.
- 森悠紀ほか(2018)『描画課題における視空間認知と運動制御の関連』臨床作業療法,35(6),621-626.
- 大竹真奈(2019)『描画による自己表現と感情調整の関連』日本心理学会第83回大会発表論文集.