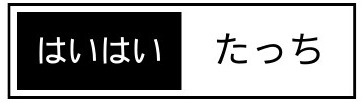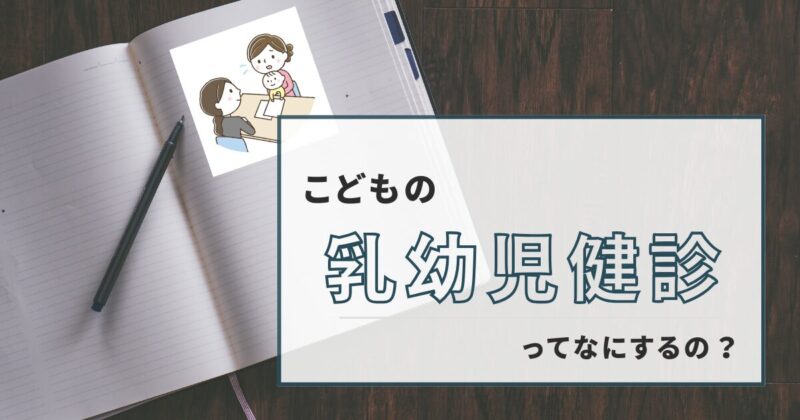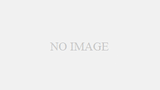はじめに
乳幼児健診は、赤ちゃんの成長と発達を定期的に確認し、健康状態や問題を早期に発見するための健診です。
日本では、母子保健法に基づいて自治体が実施しており、子どもたちの健康な成長を支えるための重要な機会になります。
検診のタイミングになると自治体から案内が届き、区役所や病院で検診を受けることができます。

お子さんの発達や子育てについて相談できる貴重な機会ではありますが、検診のタイミングや目的については詳しく認識されていない方も多いと思います。
この記事を読むことで乳幼児健診の項目や目的についての予備知識が得られるようになります。
乳幼児健診の概要
乳幼児健診はお子さんの身体的・精神的な発達に関する検査や保健師からの指導、医師の診察、お子さんの発達に関する相談などをすることができます。
乳幼児健診の目的
健康状態のチェック
身長や体重、頭囲の測定などを測定します。成長曲線という標準的な赤ちゃんのサイズをまとめた表があり、お子さんの身体の成長が成長曲線に沿って発達しているか確認します。
成長曲線は母子手帳に記載されているので、検診以外のタイミングでも身長体重であれば、ご両親がご自身で記入することも可能です。

病気や発達障害の早期発見
視覚や聴覚、運動発達などの発育状況を確認します。質問紙やご両親への質問で月齢に応じた赤ちゃんの反応などを確認します。もし発達に関する不安や心配があれば保健師や医師に相談することも可能です。検診時になにか心配があれば専門機関への紹介や、必要に応じて早期の介入や治療を行えるように情報提供を受けることができます。
育児相談の機会:
親が抱える不安や疑問に医師や保健師が答え、育児についてのアドバイスを提供します。
乳児健診のタイミング
一般的に、以下の時期に健診が行われますが、地域や医療機関によって多少異なることがあります。
1か月健診
退院後最初の健診。
新生児期(生後1ヶ月)から乳児期(生後2〜11ヶ月)に移る段階で、体重の増加や授乳の様子、黄疸の消失などを確認します。
4か月健診
身長体重の増加などに加え、首のすわりや手足の運動、視覚や聴覚の発達をチェックします。
6-7か月健診
離乳食の進み具合や、座る力、手を使った動作などを確認します。
9-10か月健診
おすわりやハイハイができるか、立つ準備ができてきているか、歯の生え具合、周囲との関わりなど社会的な反応などを見ます。
1歳6ヶ月検診
歩く・走るなどの運動発達の進み具合、周囲とのこ関わりなどの社会的な反応などを確認します。
健診でチェックされる主なポイント
身体測定
身長、体重、頭囲などを定期的に計測し、発育のペースを確認します。
運動発達のチェック
首のすわり、寝返り、はいはい、つかまり立ちなどの発達段階が正常かを確認します。
視覚・聴覚の確認
音に対する反応や、物を目で追う動作など、感覚機能の発達をチェックします。
栄養状態の確認
授乳や離乳食の進み具合、栄養バランスについてもアドバイスが提供されます。
乳児健診の重要性
乳児健診は、単に病気や障害を見つけるだけでなく、健康な成長を確認するためにも重要な機会です。
病気や障害を早期発見することができればその分早く対応ができます。対応が早いほどに将来的なリスクを軽減することができる可能性があります。
また、親が感じている育児に関する疑問や悩みを相談できる場としても機能しています。
まとめ
乳児健診は、赤ちゃんの健康と発達を見守る大切なステップです。定期的な健診を通じて、子どもが健やかに成長できるようサポートしてもらえます。万が一なにかあれば早期に問題を発見し、適切な対応を行うことが可能です。
また、ご両親にとっても育児の不安や日々の悩み事を相談できる場であり、安心感を得る重要な場となります。
引用文献
- 厚生労働省, 「母子保健に関する施策」.
- 日本小児科学会, 「乳幼児健診ガイドライン」.